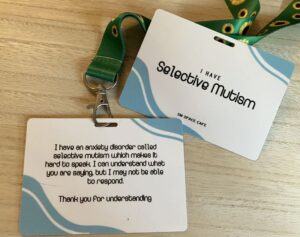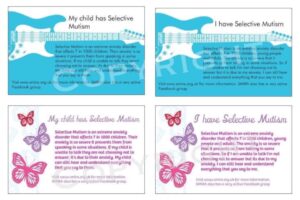ミラノオリンピック開会から既に1週間。昨夜のフィギュアスケート男子シングルのあまりにも予想外な結果に、ただただ驚愕してしまいました。王者マリニンにオリンピックの魔物がとりついたのか、はたまた13日の金曜日の呪いなのか。これまで14連勝していただけに、あの崩れ方は尋常じゃなかったですね (;^_^A
近年、ロンドンでは物価が高騰し続け、気軽に外食もできません。先日夫がもらってきた割引券を使って近隣のパブで晩御飯。息子が注文したフィッシュ&チップスにも魅かれたんですが、鴨肉のローストがとても美味しかったです。
…………………………………………………………………………………………………………………………
講演者:サラ・レヴァントさん(Sarah Levant )
米ニュージャージー州の個人クリニックで働く、公認臨床ソーシャルワーカー兼ソマティックセラピスト。発達期のトラウマやストレスなどの回復にむけ、神経系の調節サポートを専門としている。
ソマティックセラピー*への気づき
ワシントンDCでソーシャルワーカーをしていた時、トラウマを抱えたホームレスの若者達を担当していました。従来の言語や思考を中心とする心理療法やCBT(認知行動療法)を試みたものの、全く効果がなくて…。
人は今日食べるものが無い、寝るところがない、明日生きているか分からないというようなサバイバルモードにおかれると、知能指数が低下して身体がシャットダウンしてしまうーー情報を処理することが困難になるんです。そんな状態にある若者たちの目がソマティックセラピーによって変わっていくのを見て、私も学ぶ決心をしました。
(*ソマティックセラピー(Somatic Therapy)とは?
ソマティックエクスペリエンシングとも呼ばれ、1970年代にピーター・リヴァイン博士が開発したトラウマ治療のための心理療法。身体感覚に意識を向け、身体に溜まった過剰なエネルギーを少しずつ解放することで、神経系の自己調整能力を高めていく。それによって、心と身体のつながりを再構築し、心身の健康の回復を促す。トラウマだけでなく、慢性的ストレスの軽減や長期的なストレスによる不調からの回復も期待できる)
保護者のメンタルヘルスの重要性
子どもをサポートする母親は、たとえ苦しい時でも、周囲に「私は大丈夫」と言ってしまうものです。そう言うことで自分を奮い立たせている部分も大きいでしょう。情報が錯綜するこの現代社会では、人は孤立し常に批判されているように感じています。子どもの問題や今直面している問題にばかり集中して、自分の身体や心のことは後回しにしがちではないでしょうか?
あなたは食事や水分を摂るのを忘れたり、自分の健康や心の管理を忘れていませんか?
コーヒーのがぶ飲みやオンラインショッピング等でストレスを発散して、そのまま頑張り続けていませんか?
自分の気持ちや感情を調整できないままでいると、免疫系統や人間関係、睡眠、精神面などにひずみが出てきます。保護者自身が自己の感覚や感情の状態を認識し、自己調整能力を培うことで、それが心身の安定につながり、子どもや家族にも良い効果をもたらすのです。
完璧な人なんて誰もいないし、完璧な親なんていません。不完全な親でいいのです。子どもの前で「ママお腹がすいちゃった、何か食べなくちゃ」「ごめんね。今ママは疲れてるから、ちょっと休むね」と言葉に出して下さい。それが、子どもにとってのモデル行動となります。
保護者が安定していれば、相乗効果で子どもも安心できます。
常にマインドフルな状態、「今この瞬間」に意識を集中させ、ありのままの現実を受け入れてみましょう。集中力やストレスへの耐性が向上し、心が安定してきます。その状態で自分に何が必要かを感じてください。そうすることで、次にとるべき行動の準備ができるのです。
他の人たちと繋がったり、話をしたりすることも、自分の時間を持つことも重要です。一緒に黙ってベンチに座ってくれる誰か、それはペットでも大丈夫。散歩に出かけたり、子どもが寝た後お茶を飲む時間を取るなど、ストレスを減らすことを心掛けてみてください。
(みく後書き)
私自身、健康第一を実感している今日この頃ですが、身体だけでなく心の安定も必須ですよね。特に、雨ばかりの暗い毎日が続くと、自然と気持ちが沈んでしまい、ネガティブ思考になってしまう…。この講演では、実際にソマティックセラピーで何をするのか触れませんでしたが、自分の身体や心の声に耳を澄ませて、どのように自己管理能力を高めていくのか、とても気になります。
<関連記事>
保護者のメンタルヘルス SM H.E.L.P. 2025年10月サミットより(その6)
子どもとの良好なコミュニケーション2 SM H.E.L.P. 2025年秋サミットより(その5)
子どもとの良好jなコミュニケーション SM H.E.L.P. 2025年10月サミットより(その4)
保護者へのアドバイス SM H,E.L.P. 2025年10月サミットより(その3)
緘黙児の保護者として SM H.E.L.P. 2025年10月サミットより(その2)