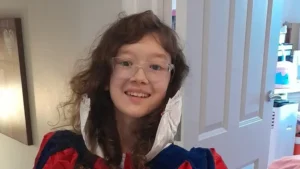動画:緘黙に苦しむ君へーーサキ君からのメッセージ
注目
ソマティックセラピー SM H.E.L.P 2025年10月サミットより(その7)
ミラノオリンピック開会から既に1週間。昨夜のフィギュアスケート男子シングルのあまりにも予想外な結果に、ただただ驚愕してしまいました。王者マリニンにオリンピックの魔物がとりついたのか、はたまた13日の金曜日の呪いなのか。これまで14連勝していただけに、あの崩れ方は尋常じゃなかったですね (;^_^A
近年、ロンドンでは物価が高騰し続け、気軽に外食もできません。先日夫がもらってきた割引券を使って近隣のパブで晩御飯。息子が注文したフィッシュ&チップスにも魅かれたんですが、鴨肉のローストがとても美味しかったです。
…………………………………………………………………………………………………………………………
講演者:サラ・レヴァントさん(Sarah Levant )
米ニュージャージー州の個人クリニックで働く、公認臨床ソーシャルワーカー兼ソマティックセラピスト。発達期のトラウマやストレスなどの回復にむけ、神経系の調節サポートを専門としている。
ソマティックセラピー*への気づき
ワシントンDCでソーシャルワーカーをしていた時、トラウマを抱えたホームレスの若者達を担当していました。従来の言語や思考を中心とする心理療法やCBT(認知行動療法)を試みたものの、全く効果がなくて…。
人は今日食べるものが無い、寝るところがない、明日生きているか分からないというようなサバイバルモードにおかれると、知能指数が低下して身体がシャットダウンしてしまうーー情報を処理することが困難になるんです。そんな状態にある若者たちの目がソマティックセラピーによって変わっていくのを見て、私も学ぶ決心をしました。
(*ソマティックセラピー(Somatic Therapy)とは?
ソマティックエクスペリエンシングとも呼ばれ、1970年代にピーター・リヴァイン博士が開発したトラウマ治療のための心理療法。身体感覚に意識を向け、身体に溜まった過剰なエネルギーを少しずつ解放することで、神経系の自己調整能力を高めていく。それによって、心と身体のつながりを再構築し、心身の健康の回復を促す。トラウマだけでなく、慢性的ストレスの軽減や長期的なストレスによる不調からの回復も期待できる)
保護者のメンタルヘルスの重要性
子どもをサポートする母親は、たとえ苦しい時でも、周囲に「私は大丈夫」と言ってしまうものです。そう言うことで自分を奮い立たせている部分も大きいでしょう。情報が錯綜するこの現代社会では、人は孤立し常に批判されているように感じています。子どもの問題や今直面している問題にばかり集中して、自分の身体や心のことは後回しにしがちではないでしょうか?
あなたは食事や水分を摂るのを忘れたり、自分の健康や心の管理を忘れていませんか?
コーヒーのがぶ飲みやオンラインショッピング等でストレスを発散して、そのまま頑張り続けていませんか?
自分の気持ちや感情を調整できないままでいると、免疫系統や人間関係、睡眠、精神面などにひずみが出てきます。保護者自身が自己の感覚や感情の状態を認識し、自己調整能力を培うことで、それが心身の安定につながり、子どもや家族にも良い効果をもたらすのです。
完璧な人なんて誰もいないし、完璧な親なんていません。不完全な親でいいのです。子どもの前で「ママお腹がすいちゃった、何か食べなくちゃ」「ごめんね。今ママは疲れてるから、ちょっと休むね」と言葉に出して下さい。それが、子どもにとってのモデル行動となります。
保護者が安定していれば、相乗効果で子どもも安心できます。
常にマインドフルな状態、「今この瞬間」に意識を集中させ、ありのままの現実を受け入れてみましょう。集中力やストレスへの耐性が向上し、心が安定してきます。その状態で自分に何が必要かを感じてください。そうすることで、次にとるべき行動の準備ができるのです。
他の人たちと繋がったり、話をしたりすることも、自分の時間を持つことも重要です。一緒に黙ってベンチに座ってくれる誰か、それはペットでも大丈夫。散歩に出かけたり、子どもが寝た後お茶を飲む時間を取るなど、ストレスを減らすことを心掛けてみてください。
(みく後書き)
私自身、健康第一を実感している今日この頃ですが、身体だけでなく心の安定も必須ですよね。特に、雨ばかりの暗い毎日が続くと、自然と気持ちが沈んでしまい、ネガティブ思考になってしまう…。この講演では、実際にソマティックセラピーで何をするのか触れませんでしたが、自分の身体や心の声に耳を澄ませて、どのように自己管理能力を高めていくのか、とても気になります。
<関連記事>
保護者のメンタルヘルス SM H.E.L.P. 2025年10月サミットより(その6)
子どもとの良好なコミュニケーション2 SM H.E.L.P. 2025年秋サミットより(その5)
子どもとの良好jなコミュニケーション SM H.E.L.P. 2025年10月サミットより(その4)
保護者へのアドバイス SM H,E.L.P. 2025年10月サミットより(その3)
緘黙児の保護者として SM H.E.L.P. 2025年10月サミットより(その2)
保護者のメンタルヘルス SM H.E.L.P 2025年10月サミットより(その6)
ミラノオリンピックが始まりましたね。日本のフィギュアスケートチームの活躍が楽しみです。イギリスは相変わらず天気が悪くて雨続き。5週間ぶりに南アジアとオーストラリアの旅から帰ってきた友達が、時差ボケが治らないとぼやいていました。
先日、ウォーキング友達の誕生日だったので、ロンドンの金融街シティ内を散策。ビル群の合間に点在する小さな庭園を巡り、遅いランチを食べてからロンドンを展望できるスカイガーデンへ
…………………………………………………………………………………………………………………………..
昨年秋に開催されたSM H.E.L.Pサミット最終日のテーマは、脳(神経系)と身体のつながりに着目し、自己調整能力を高めて心身の健康を向上させること。その対象は子どもではなく、子どもを支える側の保護者でした。保護者が自身の神経系の状態を認識し、そのニーズに応えることで心と体が繋がって、それが子どもにも良い影響をもたらすというのです。
その方法というのは下記の3つ:
- ソマティック・エクスペリエンシング(SE: Somatic Experiencing)
ソマティックセラピーとも呼ばれ、1970年代にピーター・リヴァイン博士によって開発された、身体感覚に焦点を当てたトラウマ治療のための心理療法。身体感覚に意識を向け、身体に溜まった過剰なエネルギーを少しずつ解放することで、神経系の自己調整能力を高めていく。それによって、心と身体のつながりを再構築し、心身の回復を促す。トラウマだけでなく、慢性的なストレスの軽減や長期的なストレスによる心身の不調からの回復が期待できる。
- 内受容感覚体験(interoception experience)
内容容感覚体験とは、「お腹が空いた」「心臓がドキドキする」など、自分の身体の内部の状態を感じ取る感覚のこと。呼吸、心拍、内臓の動き、体温、空腹感、喉の渇きなど、身体の生理的状態に関する感覚の総称。この感覚は、感情の認識や自己の状態を把握する上で重要であり、社会性やメンタルヘルスにも深く関わっている。内受容感覚体験を積むことで、自分自身をより深く理解し、自己調整能力を高めることができる。
- 神経発達運動(neurodevelopmental movements)
原始反射運動は乳児期に見られる脳幹由来の無意識な反応で、通常生後6〜12ヶ月で消失。それとともに身体を意識的に動かす大脳主導の神経発達運動へと移行する。原始反射運動はバランス感覚、運動能力、視覚、聴覚、発話能力、学習能力、コミュニケーション能力の発達に不可欠で、神経発達運動により脳から筋肉へ動作の指令を伝える神経回路を発達・成熟させていく。遊びを組み合わせた神経発達運動の包括的なトレーニング(感覚統合)で、脳と身体の連携を強化することができる。
保護者のメンタルヘルスの不調が、何故子どものサポートに影響するのか?良く「自分が幸せでなければ、他者を幸せにすることはできない」といいますが、それと同じ考え方なのかなと思います。保護者、特に母親は自分のことを後回しにする傾向が強く、ストレスや疲れが溜まってもそのままにしておくことが多いのではないでしょうか? セラピストに相談するといっても、日本ではまだ気軽に相談できる環境が整っていないかもしれませんが…。
保護者のメンタルヘルスや体調が不調だと、子どもは敏感に感じ取ります。疲れやストレスが溜まりすぎると、正しい判断や対応をすることが困難になるかも。また、それが体調にも影響を及ぼしますよね。自身の健康も子どもの健康も同じぐらい大切。難しいとは思いますが、ひとりで頑張りすぎないこと、忙しくても自分の時間・癒しを持つことを忘れずにいたいものです。
<関連記事>
子どもとの良好なコミュニケーション2 SM H.E.L.P. 2025年秋サミットより(その5)
子どもとの良好なコミュニケーション SM H.E.L.P. 2025年10月サミットより(その4)
保護者へのアドバイス SM H,E.L.P. 2025年10月サミットより(その3)
緘黙児の保護者として SM H.E.L.P. 2025年10月サミットより(その2)
子どもとの良好なコミュニケーション2 SM H.E.L.P 2025年10月サミットより(その5)
1月も既に後半になだれ込みましたね。昨年末に罹った風邪(インフル?)がなかなか治りきらず、日の短かさも相まって、時間がびゅんびゅん飛んで行く様な感じでした…。雨降りや曇りの日が続くどんより暗い季節に、青空がのぞく日があると本当に気が清々します。
近所の公園には、イギリスの春を告げる野生のスノードロップが既に咲き始めています。雨に濡れた蝋梅の花が冬空にひっそりと薫って
…………………………………………………………………………………………………………………………..
さて、前回の続きでジュリー・キングさん(Julie King )による、子どもとのコミュニケーションの取り方について。
<例2>
子どもが反抗的になるケース
3歳の子どもがベッドタイムになると駄々をこね、なかなかベッドに入ろうとしません。保護者はどうしてそうなるのか見当がつきません。
子どもは独立への意欲と人と繋がる意欲を両方持っています。このケースでは、母親(父親)と離れたくないという気持ちが強く、不安なのでしょう。別れと再会の遊びをスモールステップで何度も繰り返してみてください。3歳だったら、かくれんぼもいいでしょう。寝かせる時には、お気に入りの本を読んだり、ぬいぐるみを渡すなど、眠りに入る手助けをしましょう。疲れすぎると眠れなくなってしまうので要注意です。
ステッカーチャートの効果
ステッカーチャートを使うのはかまいませんが、使うことで子どもが何らかのスキルを習得することはありません。ご褒美システムを使うと、子どもが何かを交渉をしてくる可能性があります。例えば、「ステッカーが5個たまったら、〇〇を買って」など。また、「〇〇なんか要らないからやらない」という結果にもなりかねません。ステッカーチャートは最終手段として使って欲しいと思います。
ジュリーさんの息子さんがプレスクールに入った際、最初は何の問題もなく通えていたそう。でも、保育時間の長いキンダーガーデンに行き始めると、ジュリーさんにしがみついて園に入るのをしぶり始めました。ある日「今日は早めに迎えに来る」と告げたら、その日はすんなり園に入れたというのです。
実験的に園にいる時間を短縮してみたところ、しがみついて嫌がることはなくなりました。更に驚いたのは、先生から「園で全く話をしていません」と言われたこと。通う時間を短くしたところ話し始めたので、場面緘黙ではないことが判明しました。
根本的な問題は、息子さんには睡眠障害があって毎日疲れた状態で園に行っていたこと。長時間園で過ごすことが身体的に無理だったのです。子どもの生活の中で、睡眠・食事・そして感覚過負荷(sensory overload:視覚、聴覚、嗅覚などの五感からの刺激に敏感になり、脳が処理しきれないほどの過剰な刺激を受けること。心身に大きな負担がかかる)は大きな比重を占めます。周りの子ではなく、自分の子どもの様子を良く見てください。
思春期の子どもへの対応
保護者は心配でつい原因を追究してしまいがちですが、一人になって処理する時間が必要な子どももいます。一歩引いて「何か言いたいことがあったら、いつでも聞くから」と受け止める姿勢を見せてください。「どうしたの?」「何があったの?」と直球の質問をするより、「今日は元気がないね。今何か言いたいことはある?」「学校でプロジェクトはどう?時間があったら教えて」など、子どもの気持ちと自主性を尊重した言葉がけをしてください。
子どもには子どもの社会があって、大人と同じ様に悩んだり、喜んだりしていることを忘れないでください。
<関連記事>
子どもとの良好jなコミュニケーション SM H.E.L.P. 2025年10月サミットより(その4)
保護者へのアドバイス SM H,E.L.P. 2025年10月サミットより(その3)
緘黙児の保護者として SM H.E.L.P. 2025年10月サミットより(その2)
子どもとの良好なコミュニケーション SM H.E.L.P 2025年10月サミットより(その4)
明けましておめでとうございます。なんだか慌ただしくクリスマスの準備や会合などに追われているうちに、あっという間に2025年が過ぎ去ってしまいました。おまけに、大晦日前にインフル(?)を拾ってしまい、久しぶりにダウン…。
クリスマスツリーを飾っておくのは、12夜にあたる1月5日まで。今年のクリスマスは珍しく抜けるような青空が広がり、義母宅の庭には冬の実や花が
…………………………………………………………………………………………………………………………..
講演者:ジュリー・キングさん(Julie King )
2歳から10代の子供を持つ親へのコンサルティング、オンラインワークショップの開催、専門研修の提供、全米および海外の学校、企業、保護者団体への講演活動を行う。ジョアンナ・フェイバーさんと『幼い子どもが聞いてくれる話し方:2~7歳の子どもとの暮らしサバイバルガイド(How To Talk So LITTLE Kids Will Listen: A Survival Guide to Life with Children Ages 2-7』他、ベストセラー2冊を共著。
子どもの感情を考慮に入れる
親は知らず知らずのうちに子どもが期待通りに行動をすることを望むもの。その期待が裏切られた時、どうしたら子どもの行動を変えられるかに捕らわれ、心穏やかでなくなります。反対に、子どもから見ると「お母さんが怒っているから怖い、嫌だ。自分が悪いんだ」とネガティブな感情を抱くのです。
覚えておきたいのは、子どもがどう感じたかが直接子どもの行動に出るということ。もし子どもの行動を変えたいのなら(子どもに正しい行動をさせたいのなら)、子どもの感情に着目する必要があります。もし子どもが、あなたの言うことを正しいと感じたなら、正しい行動をするはず。でも、そう感じられないから、正しい行動ができないのです。
頭ごなしに決めつけない
親に「どうして〇〇できないの?」と言われた子どもは、自分が駄目だ・悪いと感じ、自己防衛に走ります。「どうして〇〇できないの?」は質問ではなく、批判です。子どもは責められたと思い、嫌な気持ちになって「お母さんとは話したくない」という態度に。注意すればするほど頑なになる傾向も。保護者はこうした状態にならない様に、考え方をシフトする必要があります。
<例1>
トレーナーを学校で脱ぎっぱなしにして、忘れてきてしまう子どもがいたとします
どうして子どもは忘れてしまうのか?
大人でもよくあることですが、何か夢中になっていたり、後で回収しようと思ってそのままにしてしまったかもしれません。トレーナーの存在自体を忘れてしまったのか、トレーナーを置いた場所を忘れてしまったのか、それとも時間がなかったのか…。どうしてそういう行動を取ってしまうのか、子どもの心の動きにも興味を持って下さい。
車の運転を考えてみてください。免許を取り立ての時は、色々なルールに細心の注意を払いますが、そのうちに慣れて自動的になります。トレーナーを脱ぎ捨てないことを習慣化させるためには、心の中で練習したり、絵に描いたり、注意喚起させる何かを見つけたりするのも一案。これはコミュニケーションスキルではありませんが、何かを習慣化させる時に役立つスキルです。
まず子どもと静かに話す
子どもの口から、どんな時にトレーナーを脱いで、どんな風に考えて置いてきてしまうのかを、共感しながら聞き、本人と問題解決の方法を考えるようにしましょう。
学校にトレーナーを着ていくこと自体をやめる、脱いだらすぐ腰に巻く、脱いだらすぐに教室のフックにかける、校庭に出る前にロッカーに入れる、脱いで置いた場所を心にとどめる、教室に戻る際に「トレーナーはどこ?」と気に掛ける等の方法があるかと思います。
子どもの気持ちを想像して、「休み時間に校庭に出て思いっきり遊びたいよね。遊んでいるうちに暑くなるから脱いで、すごくいい気持ちになるね」と口に出して言ってみましょう。会話をしているうちに、子どもが「他の子は誰も着てないよ」などと話始めるかもしれません。
子どもの話を聞いてから、「でも、校庭に脱ぎ捨てて誰かに踏まれちゃうのは嫌だね。どこかいい場所はないかな?」などと質問。それからまた、子どもの意見を聞いて下さい。
「何回なくすの?!」と非難する前に、失くしたらまた買わなければならないことを手短に告げ、明日も同じトレーナーを着ていくにはどうしたらいいか相談してください。くどくど小言を言われるのは、誰も好きではありません。
会話を重ねると、子どもが自分で方法を考える様になります。大人は自分ができているから子どももできると考えないこと。
長いので次回に続きます。
<関連記事>
保護者へのアドバイス SM H,E.L.P. 2025年10月サミットより(その3)
緘黙児の保護者として SM H.E.L.P. 2025年10月サミットより(その2)
保護者へのアドバイス SM H.E.L.P 2025年10月サミットより(その3)
イギリスでは1週間ほど前から冷え込みが厳しくなってきました。冬時間に変わってから日が短くなり、どんより曇り空が続く毎日。そんな中、太陽と青空を見ると本当にほっとします。
すぐ変わる天気予報とにらめっこの今日この頃。ウォーキングや散歩、外出が晴れの日に当たったら超ラッキー
………………………………………………………………………………………………………………………….
講演者:ルース・ペレドニクさん(Ruth Perednik)
心理士でエルサレムにある場面緘黙治療センターの所長。息子さんが場面緘黙を患ったことをきっかけに、緘黙に苦しむ子どもや十代の若者の治療に情熱を注いできた。
家族全員の理解を
緘黙児の両親に多いのは、ひとりが熱心な支援者でもうひとりはそれほど関わっていないケース。両者ともにSMについて学び、家族全員を教育する必要があります。緘黙の子どもに対して、どんなスモールステップを計画していて、家族がどの様な態度を取ればよいかを全員に理解してもらうこと。
祖父母に理解・協力を求める
祖父母はスライドインに使える貴重な要員であり、祖父母から他の親戚へと子どもの世界を広げていくことができます。SMを言葉で説明するのが難しい場合は、映像や緘黙のドキュメンタリーを見せるのが効果的。それでも「ちゃんと挨拶しなさい」と子どもにいう場合は、わざと話さない訳ではないことを説明し、「すべきこと」「してはいけないこと」を具体的に伝えてください。
祖父母や親戚の方へ
久しぶりに会っても目も合わせず、言葉も発さない孫に、祖父母としては傷つくかもしれません。でも、パーソナルなことと捉えないようにしてください。
「挨拶しなさい」ではなく、返事がなくても笑顔で「よく来たね」と声をかけてください。会話の有無にかかわらず、子どもが好きな遊びを一緒にやって、自分たちも楽しみましょう。自分たちの理想や一般論を押し付けるのではなく、子どもの今をそのまま受け止めて。子どもがそこにいること、一緒に何かできることが大切なのです。非言語のコミュニケーションでも信頼関係を築くことができます。
きょうだい児への配慮
緘黙児の兄弟姉妹(きょうだい児)にもきちんと説明・理解してもらうことが重要。自分が構ってもらえないジェラシーを抱え続けていたり、「お前の妹、話せない」などと同級生などに言われて傷つくことも。SMは克服可能であることを説明し、状況や年齢に合わせて、その時々に何が起こっているのか、どうしたら助けることができるのかを説明しましょう。短くてもいいので、きょうだい児と1対1で向き合える時間を作ってください。
成長したら治る訳ではない
多くの緘黙児は学業には問題なく学校生活を送れていて、話せないかもしれませんがちゃんと友達もいます。そのため、周囲は子どもが話す気になるまで待とうと考えがち。でも、子どもが自分だけの力で克服することは困難です。思春期の子どもは不安のために他の不安障害を発症してしまう可能性もあることを忘れないで。焦る必要はありませんが、同級生たちはスポーツや習い事など、どんどん社会的な経験を積んでいることも心にとめておきましょう。
もし成人だったら、自分で病院に行ったり、薬を飲んだりできます。でも、子どもは大人に依存するしかありません。学校で一日話せなくて、どんな気持ちで無言の時間を過ごしているのか、それが子どもの自己肯定感にどんな影響を与えているか…。
毎日の暮らしの中で話せないこと、質問に答えられないこと、自分から何もできないこと、要求を口にできないことーー周囲の人間が気づいて配慮することで、随分違ってきます。全く知識のない人に説明するのは大変かもしれません。でも、サポートネットワークの輪を広げていくことは、子どもだけでなく保護者のためにも重要です。
<関連記事>
緘黙児の保護者として SM H.E.L.P. 2025年10月サミットより(その2)
緘黙児の保護者として SM H.E.L.P 2025年10月サミットより(その2)
イギリスは先月末に夏時間から冬時間に変わり、どんどん日が短くなってきました。今秋は例年になく暖かで、春夏の日照時間が長かったためか紅葉がきれいです。といっても、落葉樹の葉はかなり散り始めていて、もうあたりは晩秋の風景。
今年のアメリカ蔦も、紅葉も例年より赤かったような…。街角の郵便ポストには児童書のキャラクター達の編みぐるみが
…………………………………………………………………………………………………………………………..
講演者:ジョリーン・ファーナルド博士(Dr. Joleen Fernald)https://www.joleenfernald.com/
乳幼児期における精神保健学の博士号を持ち、フロリダ州で神経多様性を尊重する診療所を運営。場面緘黙の子どもたちに使用するDIR(The Developmental, Indidual-difference, Relationship-based)-SMカードデッキを出版している。
緘黙児の親としての道のり
ファーナルド博士の娘さんが場面緘黙(SM)になったのは、今から21年前のこと。まだインターネットが普及しておらず、SMが知られていなかった時代でした。言語療法士の資格も持つ彼女でさえ、SMに対する知識はなかったといいます。
「当時3歳だった娘は、恥ずかしがり屋で臆病なところがあり、音に対する強い感覚過敏がありました。家では自信たっぷりに話すのに、外に出たとたん貝のように押し黙る…」
当時、SMの原因はトラウマと考えられており、診断までに随分時間がかかったそう。治療してくれる専門家が見つからず、緘黙について学びながら自身で治療にあたることに。
ファーナルド博士は娘さんとSMについてオープンに話し合い(年齢相応に)ながら、小さなステップを積み重ね症状を改善させていきました。
もちろん、目標は話すことですが、そこに行きつくまでの小さなステップのひとつひとつが大切だと話します。
「一歩進んで三歩下がるといった感じで、落胆して泣きたくなることも多かったわ。緘黙児はそれぞれ違うから、子どもも支援者も常に手探りで学んでいる状態。だから、失敗してもいいんです。失敗を振り返って、更に細かいステップに分けてみたりと、子どもに合った工夫を重ねていければ大丈夫」
例えば、「こんにちは」と言えなくても、スクールバスから手を振るだけで大きな進歩。それを支援チームみんなで喜ぶことで、次に向かう勇気がわいてきます。反対に、失敗したときは一緒に支え合うことが大切。
娘さんは早くから「SMは特定の場所で言葉を出しにくい症状」と説明を受け、理解していたそう。言語能力が高く、大好きだった『オズの魔法使い』の中の臆病なライオンをよく引き合いに出していたとか。
彼女たちは発話以外にもっと多くの挑戦ができる様、抗不安薬の服用にも踏み切りました。娘さんはこの薬を「勇気がでる薬」と命名。積極性が出てきて、かなりの成果があがったそうです。
SMの背後にあったもの
「実は、娘には気がかりな点がありました。同年代の女の子とは興味の対象が全く違っていて、社会性の遅れが明確だったんです。ASD(自閉症スペクトラム障害)ではないかと疑っていたんですが、色々な専門家に相談してもずっとグレーのまま。今考えると、娘はマスキングが上手かったんでしょうね」と当時を回想します。
「思春期になっても、娘にはお洒落をしたり、恋愛をしたり、遊びに出かけたりといった経験が全くなくて。社会性では妹にも追い越されてしまい、親としてはすごく落胆したし、悲しかったわ。娘は一生友達も恋愛もできないんじゃないかと悩みました」
この疑惑は、コロナ禍にドキュメンタリー番組を観ていた時に解けました。ASDの主人公の女の子を見て、娘さん自身が「私にそっくり」と気づいたからです。
最終的にASDの診断が下りたのは19歳の時でした。家族は娘さんの性格やそれまでの行動に納得し、安心できたといいます。
娘さんは、今では結婚して家庭を持ち、幸せに暮らしているそう。
「保護者はどうしても『普通の子のように』と望んでしまい、失望や落胆や悲しみを感じるでしょう。でも、今何が起こっていようと、どんなに大変だろうと、それは今だけのこと。子どもは日々必ず成長していくものです。明日、来年、5年後にはどうなっているか誰にも判りません。今子どもができて嬉しいことは何か?今子どもとの絆を深められることは何か?子どもが今できることに焦点を当て、子どもとの時間を楽しみましょう」
近年、脳の多様性が重んじられる様になり、その人らしく生きるという考え方・フレームワークが主流になってきています。多様性があるからといって、決して人より劣っている訳ではありません。子どもに診断名を告げることは昔より楽になってきているといえます。
子どもにどんな診断名がつこうと、今までと変わらないあなたの子どもだということをどうか忘れずに。
<関連記事>
告知することの重要性 SM H.E.L.P. 2025年10月サミットより(その1)
今秋もアメリカのケリー・メルホーンさん主宰のSM H.E.L.P.が、恒例のオンラインサミットを開催。今回のテーマは神経心理学による診断・子どもへの告知から、子どもを支える家族のメンタルヘルスケアに至るまで、ますます裾野を広げた内容になっていました。
ロンドンは街じゅうがハロウィンの飾りだらけ。31日の今宵は生憎の雨となってしまいましたが、子ども達が”Happy Halloween!”と大勢やってきました
…………………………………………………………………………………………………………………………..
講演者:リズ・アンゴフ博士(Dr. Liz Angoff)
神経心理学の専門医資格を持つアメリカの教育心理士。20年にわたり学校神経心理士として勤務した後、自らの診療所を設立。脳の多様性を持つ子どもとその家族が、子どもの脳の特性を理解し、子どもの考え方や感情を支援していけるよう尽力している。
神経心理学(Neuropsychology)とは?
近年の研究により、発達障害がある子どもの脳は通常の子どもの脳と機能に違いがあることが確認されています。この脳機能の特性の違いが、コミュニケーションや行動に影響を及ぼすと考えられています。現在では、この違いを多様性として捉え、互いに尊重し合い、活かしていこうという考え方が主流になってきました。 神経心理学では、人の脳と神経系が行動や認知機能にどのように関連しているかを研究。神経心理学士は臨床評価と認知機能検査を組み合わせて患者のもつ課題を理解し、管理と治療のための方針・対策を決めます。
子どもが持つ負のイメージを覆すために
脳/神経の多様性(neurodiversity)がある大人と話すと、それぞれの発達障害が何であれ全員が同じことを言います。「小さい頃から自分が他の子達と違うのは判っていた。自分はバカで、のろまで、怠け者で、駄目なんだって…」。
彼らの話から見えてくるのは、幼少期から自分に対して否定的な負のイメージを持ち続けてきたということ。
私たち神経心理士が目指すのは、子どもが創りあげた負の自己イメージをくつがえし、自信を持って生きられるようにすること。そのためには、保護者だけでなく、子ども本人にも(年齢相応に)自らの脳の働きを説明し理解させることが重要になってきます。
どの段階で神経心理士に相談するか?
例えば、学校での発表が不安な子がいたとします。発表について子どもと話したり、落ち着くための呼吸法を教えたり、不安を和らげるためのセラピーを受けさせたり、学校に支援を求めたり、というのが第一段階の介入です。
それでも根本的な問題が解決せず、疑問や混乱が残る場合、次のレベルとして神経心理学が使われます。
私が良く使うメタファーは、私たちの脳は常に建設途上で、新たな回路やコネクションを常時作り続けているというもの。どの回路の性能が良く、どの回路の性能が悪いかーーよく使う回路は効率的で安定しており、中には高速回路もあるかもしれません。反対に、工事中の回路はショートしたりと不安定です。保護者に求められるのは、子どもが脆弱な回路を使わなければならない時、その回路をどう強化していくか。また、その回線が使えなければ、新たな回路を開発していくことです。健常児が使う典型的な回路が有効でない場合は、その子に合う新たな回路を見つけるよう支援します。
場面緘黙の子どものケース
場面緘黙の子どもの場合は、不安の背景にあるものは何かを探ります。例えば、他の神経系の問題として ASDやADHD、学習障害などが根源にあることも。また、不安になりやすい神経系統に生まれついた子もいます。
アセスメントは子どもに複数の活動(非言語のものが多数)を行わせる他、保護者や子どもを良く知る教師などに問診をします。そうして、子どもが情報をどう処理して、世界をどう捉えているかを理解していきます。
場面緘黙の子どものアセスメントにおいては、子どもが安心して自由に話せる場が限られているため、保護者の助けが必須。「得意なこと・苦手なことは?」「もし魔法の杖があったら、変えたいことは何?」など、保護者が子どもに訊くよう指導することもあります。
診療所、家庭、学校などから集めた情報を元に、アセスメントの評価を行います。その評価を元に診断を下し、治療・支援方法を考えていきます。
アセスメントと診断・告知の手順
- アセスメントを始める前に、本人に後で結果を教えると告げる
- アセスメントを行う
- 脳がどう働いているかを解析したら、その情報をシェアしていいか子どもに確認する。子どもにも参加させ、意見を言う場を与える
- 保護者に子どもの脳の特徴と診断名を告げ、支援方法を話し合う
- 子どもに脳の特徴・診断名を告げ、今後どうしていくかを話し合う
- 高速回路(得意分野)は何か?
- 脳が工事中のところ(不得意分野)は何か?
- 今頑張って進歩していると思えるところは?(例えば、自転車に乗ること、特定のPCゲームなど)
- 日常生活で困難なところは?
- 診断名を告げる時は、世界中に同じ様な子がいること、子どもの持つ良い面(集中力がある、観察力が鋭いなど)を強調する
- 子どもを交えて、今後の方針・計画を立てる
…………………………………………………………………………………………………………………………..
みく注:
私が勤めている特別支援学校(高機能ASD児専門)でも、脳の多様性の理論が浸透していて、それぞれの生徒が自分らしく生きられるよう支援しています。本人が自分の特性を知り、それをどう生かしていくか、苦手な部分をどうカバーしていくかが課題。書字障害がある子が試験の時にワープロを使ったり、ADHDの子が頻繁に小休憩を取ったり。周囲の理解と協力がどんどん広がっていくといいなと願っています。
<関連記事>
10月は場面緘黙の啓発月間
気がつけば、もう今月も半ばに突入。昨日、10月10日は世界精神保健連盟(WFMH)が定めるメンタルヘルスデーでした。10月はメンタルヘルスの啓発月で、イギリスでは毎年この時期になると場面緘黙がメディアに取り上げられます。今回ご紹介する記事は昨年3月にBBCエセックスニュースに掲載されたものですが、よりインパクトが強いと思い翻訳してみました。
…………………………………………………………………………………………………………………………..
場面緘黙:『人は私のことを礼儀知らずとみなすけど、本当は恐怖で凍り付いてるの』
英国エセックス州に住むデイジー・メイさん
デイジー・メイさんが成長していく中、家族は彼女がただ内気なだけだと思っていました。しかし、見知らぬ人の前での頑ななまでの沈黙は、実は場面緘黙(SM)だったのです。
この不安障害のため、エセックスに住む12歳のデイジーさんは、両親以外の人とほとんど話すことができません。
NHS(英国国民保健サービス)によると、場面緘黙は特定の社会的状況でフリーズ反応を引き起こす外的な症状で、本人は不安やパニックに陥っていると言われています。
この症状のためにデイジーさんは友達を作ることができません。しかしながら、ダンスやオンライン動画を通して演技をすることに情熱を見出し、自分を表現して自信を持つことができるようになりました。
メールで行われたインタビューで、デイジーさんはSMが日常生活にどのような影響をもたらしているか、自分自身の言葉で語ってくれました。
楽しみは、ダンスとオンライン動画制作で自分を表現すること
「想像してみてください。毎日の生活の中で人と交流する時、体はそこにあるのに口が動かず、不安で言葉が出ません。頭の中は空っぽなの。周りの人たちが話しているのを見ても、自分は話せない――行き詰まってしまう。トイレに行きたくても、どこにあるのか訊ねることさえできません。
これが場面緘黙を抱える私の人生。
ただただ言葉が見つからない。家の外では、たとえ言葉が浮かんだとしても、怖すぎて固まってしまうんです。何の助けも求めることができず、笑ったりおしゃべりすることもできない。
周りの人は、私のことを無関心でフレンドリーじゃないと思っています。不愛想な子だと。まるで、自分たちと同じ世界の人間じゃないみたいに。
私は一人ぼっち。
友達は1人もいません。私は「友達はいらない、1人でいたい」と言っています。でも、友達同士が一緒にいるのを見ると、いいなって思う。でも、誰とも話せないから、私には無理でしょうね…。家族ともまともに話せず、人と会った後はすごく疲れてしまいます」
母親のルイーズさんと一緒に舞台に立つことで、演技を通して自信を深めてきた
「昨年パントマイムに出演した時は、母とは更衣室が別でした。他の子たちはゲームをしていたけれど、私は参加できず側で見ているだけ。話すことも参加することもできないから、ただ傍観するだけでした。
でも、私は人真似がすごく得意で、家に帰って母に彼らの会話の内容を全部説明できるんです。皆が何を言っていたかちゃんと覚えています――皆は私が関心を持ってないと思っているかもしれないけれど、すごく興味があるので。
でも、演技をしている時は別。話すことはまだできなくても、その力があるように感じじられるんです。皆と一緒にショーに参加している時だけが、何かできるように思える唯一の時間です。一人ぼっちじゃない。
私は人と一緒にいること、そして大勢の観客の前で演技することが好きです。大勢の人がいるけれど、彼らは私が話しかけることを期待していないし、しっかりリハーサルするから演技には自信があります。
私は耳栓をしなければならないけれど、音楽が好きなんです。観客が笑顔になって、拍手してくれて、私を見てくれるのが好き。そうしたら、私も笑顔になれて、違う人間になれるから。
今月初め、「Uniquely Me(ユニークな私)」というチャリティ・タレントショーを開催しました。何週間も練習して、なんとか短いスピーチもすることができたんです。
彼女は今後、もっと多くの募金活動や啓発イベントを開催したいと考えています。
「特に、私と同じような人たちに才能を発揮する機会を持ってもらいたいと思って、タレントショーを開催しました。誰でも参加できて受け入れられる場――私がいつも感じる疎外感がない場を。
参加してくれた子どもたちは、様々な背景、文化、障害を持っていましたが、皆で一緒に幸せに過ごすことができました。イベントが上手くいって、人々に場面緘黙について知ってもらえたのがとても嬉しくて、また開催したいと思っています」
デイジー・メイさんは緘黙のせいで他の子どもたちと話すことができないため、友達はいらないと自分に言い聞かせようとしてきました。
「誰も場面緘黙症が何なのかを理解してくれません。私が話さないと大騒ぎするか、完全に無視して諦めてしまうかのどちらかです。人付き合いが悪いわけじゃなくて、人は好きなんだと説明できればいいんですが…。
場面緘黙と書かれたストラップを首から下げて、周りの人に理解してもらいたいです。自閉症の人と同じように。手話を習おうとしましたが、誰かの前で固まってしまうと腕も何も動かないから、難しいです。
私は自閉症なので、将来のことはあまり心配していません。将来のことを話したり想像したりするのが苦手だからあまり考えませんが、ママがすごく心配していることは知っています」
デイジー・メイさんの母親、ルイーズさんは、『Uniquely Me』の後、他の保護者たちから、このショーが子どもたちの自信を高めるのに役立ったという手紙を受け取りました。
ルイーズさんは娘が見逃してきたものについて心配しています。
「私は毎日娘の将来を案じています。デイジー・メイは何でも私に頼っているから。娘はお店で簡単なことさえ頼むことができないんです。緊急事態に自分で対処できないだろうと思うと、ひとり放っておくことはできず、本当に辛いです。
娘は一度も友達と遊んだり、お泊まりに行ったこともないから、どこかで何かを頼んだり、自分の要求を伝えたりすることはできないでしょう。もし私に何かあったら彼女はどうなるのかと、不安でなりません」
BBCエセックスニュース 記者:レイチェル・マクメネミー
https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-essex-68388212
<関連記事>

にほんブログ村
息子の緘黙・学童期 7~8歳(その23)ジュニア移行への支援1
もう9月も半ば過ぎですね…夏休みが終わって新学年度に突入し、新たな時間割で普通の日々が戻りつつあります。最近は、青空だったのが突然土砂降りになったりと、変わりやすい秋の天候。どんどん日が短くなり、急速な秋の深まりを感じています。
広葉樹の葉が少しずつ色づき始め、近くの公園もすっかりり秋の装い
……………………………………………………………………………………………………………………..
ジュニアSENCoとのミーティング
インファント(5~7歳)の校長先生を通して、早々とジュニアスクール(8~11歳)のSENCoに会えることになりました。主人に出社時間を遅らせてもらい、予定通り夫婦で出席。その際に準備したのが、下記の『息子取り扱い説明書』でした。
- 息子の緘黙状態: クラスの誰とでも話せるようになり、囁き声が徐々に普通の声になりつつある。ただ、教室内での担任との会話は短く、クラス全体や大きなグループ活動ではまだ声が出にくい。
- 社会不安など: 人目や人の評価を極端に恐れ、、「見られている」と自意識過剰になる。特に、全校生徒が集まるダイニングルームで食事をすることが不安。
- 感覚過敏: 敏感肌で聴覚や臭覚が鋭い。不安になるとその傾向が増すため、食べ物の匂いが充満し騒がしいダイニングルームでは、大きな不安に陥っていると思われる。
- ダイニングルームでの注意点:息子は食べるスピードが遅く、緊張するとさらに遅くなる。早く食べるよう促すのは逆効果なので、スタッフにその旨を伝えて欲しい。
- 着替え:体育や水泳で着替えているところを人に見られるのを嫌う。人が少ない場所を探し、着替えにも時間がかかるが、温かく見守って欲しい。
- 競争的な状況:全員が一斉に何かをしなければならない場面では、雰囲気に押されてすぐ行動に移せない。本人はやりたい、参加したいと思っているので、遅れても他の子と同じようにやらせて欲しい。
- 読み書き: 完全主義的な傾向があり、間違えたくないという思いが強い。特に作文に苦手意識があるため、やりたがらないかもしれない。音読は現在「静かな声(quiet voice)」で読んでいるが、囁き声に戻ってしまう可能性も。そうなった場合は、声が聞こえる様に近くに座り、声が大きくなるにつれて少しずつ距離を取って欲しい。音読の評価をする際は、自宅で録音するオプションも考えて欲しい。
息子の緘黙の状態・特徴、担任(学校側)にして欲しいこと・欲しくないこと、困った時の対策など、要点をできるだけ簡潔にまとめてA4の紙に印刷。それまでの経験から、多忙な教職員には分厚い資料や書籍などを渡しても見てもらえないことは学習済でした(希望された場合は別)。
ジュニアのSENCoは担当になってまだ1年目ということでしたが、私たちの話を真剣に聞いてくれました。そして、3学期中に新しい教室を放課後訪問できる様に新担任にかけあってくれることになったのです。
<関連記事>
息子の緘黙・学童期6~7歳(その3)2年生1学期の指導プラン
息子の緘黙・学童期6~7歳(その5)持ってる先生と持ってない先生
息子の緘黙・学童期6~7歳(その11)ナッツアレルギーの診断
息子の緘黙・学童期6~7歳(その18) 2年生1学期のIEPの評価
息子の緘黙・学童期6~7歳(その19) 小2 2つ目のIEP
息子の緘黙・学童期6~7歳(その20)プール恐怖症と水泳のステップ
息子の緘黙・学童期6~7歳(その21)インファントのSENCoと対立
息子の緘黙・学童期6~7歳(その22)ジュニア移行への支援1

にほんブログ村
息子の緘黙・学童期 7~8歳(その22)ジュニア移行への支援1
来週からもう9月ですね。イギリスでは8月の中盤から天候が崩れ、曇りがちの空の下秋の気配がそこかしこに。先日、主人にWindowsのアップグレードをしてもらったところ、何故か中古のPC2台とモニターが全滅…。PCを新しく買いなおす羽目になって、予想外の出費が痛かったです。
久しぶりにハイゲートウッドを訪れると、森はすっかり秋の風情。夏休みが終わってしまうのが淋しい…
…………………………………………………………………………………………………………………………..
さて、前回の続きです。
「子どもが自意識過剰にならない様、何もお膳立てしない方がいい」というインファントスクールのSENCo (Special Educational Needs Coordinator 特別支援コーディネーター) の助言を無視し、私たち夫婦はまずインファントの校長先生に手紙を書きました。自分たちでジュニアのSENCoに連絡することもできたのですが、校長を通して依頼した方が良いと考えました。
その内容は:
- 息子の場面緘黙(簡単な説明)は改善されつつあるが、ジュニアへの移行で症状の後退が懸念される
- 2年に進級した際に後退があり、戻すのに1学期かかった
- この1年間の進歩をキープできる様、環境がガラリと変わる3年に進級する際に何らかの支援をお願いしたい
- 新学年が始まる前に、新たな担任と教室に慣れておくことが重要だと思われるので、できるだけ早くジュニアのSENCoに会って相談させていただきたい
- ジュニアスクールの建物に慣れることができる様、夏休みはジュニアの講堂で行われるサマースキームに参加する予定。その際に、可能であれば新教室を訪問できたらと思っている。無理な場合は夏休み前に放課後の教室訪問ができればありがたい
- 内気な息子の性格に合うバディ (上級生のお世話係:ジュニアにあがる3年生に全員つく) を選んで欲しい。できることならば、担任は優しい女性をお願いしたい
今見ると、かなり図々しいお願いばかりですね (;^_^A でも、若い校長先生は「できるだけ対処します」と言ってくれて、すぐにSENCoとのアポを取ってくれました。
数えてみると、なんともう18年も前の話になるのですが、毎日つけていた日記を含め当時の記録が大量に残っています。読み返してみると、少しでも息子の緘黙を治したいと必死だった頃のことが鮮明に思い起こされます。
当時は、1対1や小グループならクラスメイト全員と話すことができ、あとは出欠の際の返事、教室での担任とのやり取り (単語はでるが、文章では話せない) やクラス全体&大きいグループで活動の際に声が出ないという状態。やっとここまで来たという感じでした。
イギリスでは長い夏休みの後、9月に新学年が始まるので、ただでさえ学校やクラスの雰囲気に馴染むのに時間がかかりそう。その上、環境がガラリと変わるため、もしかしたらまた話せない状況に逆戻りしてしまうかも、と不安だったのです。
学校にお願いするのも、周囲の人に助けを求めるのも、結局のところ個人的な作業になります (学校や周囲の環境が整っている場合は、必要ないかもしれませんが) 。緘黙児の保護者は内気な傾向が強いかと思いますが、遠慮していては前に進めません。勇気を出してお願いしてみましょう。駄目でもともと、やってもらえればラッキーという感覚で、メゲずにマイペースで頑張って下さい。
<関連記事>
息子の緘黙・学童期6~7歳(その3)2年生1学期の指導プラン
息子の緘黙・学童期6~7歳(その5)持ってる先生と持ってない先生
息子の緘黙・学童期6~7歳(その11)ナッツアレルギーの診断
息子の緘黙・学童期6~7歳(その18)2年生1学期のIEPの評価
息子の緘黙・学童期6~7歳(その19) 小2 2つ目のIEP
息子の緘黙・学童期6~7歳(その20)プール恐怖症と水泳のステップ
息子の緘黙・学童期6~7歳(その21)インファントのSENCoと対立