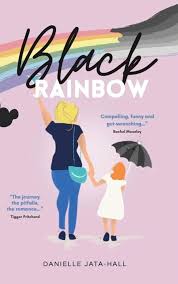3月も後半になり、イースターの長期休暇まであと1週間。急に暖かくなったかと思うと、また気温が下がったりして、寒暖差が激しい今日このごろです。
でも、野外はすっかり春の様相。花屋さんの店先は季節の花々があふれています。
……………………………………………………………………………………………………………………………
さて、またまたSM H.E.L.P. 秋サミットの続きです。今回はSMとASD併存のケースについて。
クレア・キャロルさんは教育心理学者として20 年近いキャリアを持ち、英国マンチェスターの One Education に所属。教育現場における神経多様性のある子ども達のためのプロジェクトに参加している。ASD(自閉症スペクトラム障害)の息子さんにSM(場面緘黙)の症状があったため、2014 年に場面緘黙の追加トレーニングを受講。2017 年に英国の場面緘黙支援団体 SMiRA の理事に就任している。
2018年北欧で発表された論文からの抜粋
ステファンバーグ等の研究(『ASDとSMを併存する児童(Children with Autism Spectrum Disorders and Selective Mutism: Steffenburg H, Steffenburg S, Gillberg C, Billstedt E. )』によると、北欧におけるSM発症の平均年齢は 4.5 歳。診断時の平均年齢は 8.8 歳でした。男女比では女子の方が多く(男子: 女子 = 2.7: 1)、研究グループの63%(2/3)がASD(男女差なし)であることが判明。 ASDを併存するSMグループは、症状の発現が遅く、診断時の年齢が高く、言語遅延の病歴はより多く、境界線IQまたは知的障害の割合が高いという結果が出ています。
ASDと場面緘黙の併発率について
イギリスではつい最近までASDとSMが併存するという診断を下しにくい状態にありました。これは、ASDが一次障害として上位診断されていたためです。
SMiRAが現在行っている調査によると、参加した264名の家族のうち自信を持って緘黙のみと答えたのは全体の28%。 残り72%の家族は他の疾患を併発していると考えており、その中ではASDの疑いが最多。その内、85%は診断がおりておらず、62%がASDの診断中・または診断待ちの状態です。
ASDで話さない子と、ASDとSMを併発している子との違い
Non-Verbal (言語を伴わない)のASD児はどこでも話せませんが、ASDとSM併存の子どもは場所によっては話せるという明確な違いがあります。SMの基準は全く話せないということではなく、普段の様に話せないということ。また、自発的に話すことができず、少しだけ返答をするケースも考慮に入れなくてはなりません。
イギリスではここ5年の間に、ASDに対する考え方が変わってきています。 ASDであることを肯定的に捉えてサポートする動きに変わりつつあるのです。社会的スキルのトレーニングに重点を置くのでなく、ASDの若者のニーズを分析・考慮し、彼ららしく人生を歩いていける様にサポート。彼らがしたいこと、家族が望むことを応援し、やりたくないことは絶対に強要しないといううスタンスを取っています。
ASDにSMが加わるケースを調査していくと、どうして緘黙になるのか、通常とは異なる原因が見えてくるといいます。一般的に、ASDではないSM児においては、人に話しているところを見られる恐怖や社会不安が大きな要因。一方、ASD児は不安のために圧倒(overwhelmed)された状態に陥り、そのせいで緘黙になっていると考えられます。この場合、話せないだけでなく、身体が硬直している場合が多く、部屋の片隅でひとり突っ立ったままということも。
こうしたケースでは、話せない環境そのものに目を向ける必要があり、通常のスモールステップは有効ではありません。
ちょっと長いので次回に続きます。
<関連記事>
緘黙児が持つ特性や症状 SM H.E.L.P. 2024年10月サミット(その1)
場面緘黙と併存しうる不安障害 SM H.E.L.P. 2024年秋サミットより(その2)
全般性不安障害の可能性? SM H.E.L.P. 2024年秋サミットより(その3)
場面緘黙と他の不安障害の併存 SM H.E.L.P.2024年秋サミットより(その4)
場面緘黙と社会不安障害 SM H.E.L.P. 2024年秋サミットより(その5)
場面緘黙と強迫性障害 SM H.E.L.P. 2024年秋サミットより(その6)
場面緘黙とPDA(病理学的要求回避) SM H.E.L.P. 2024年秋サミットより(その7)

にほんブログ村