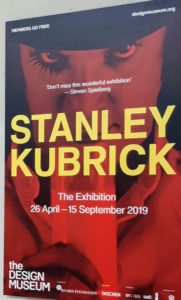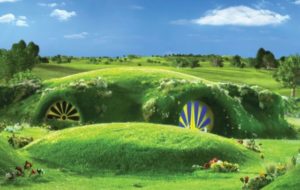イギリスは相変わらず雨模様の日が続き、今朝やっと晴れたと思ったら、また雨雲が…。6月だというのに、室内で洗濯物を乾かす日々です。


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
一番手の『SMとASD』がものすごく長くなってしまい、ここでやっと二番目の講演に移ります(^^;)。イングランド中部のノーサンプトン州における、場面緘黙のケア・パスウエイ(ケアルート)です。
イギリスのNHS(国民保健サービス)におけるSM治療は、住んでいる地区の方針によって千差万別です。また、学校によっても異なってくるため、まるで宝くじのよう。ノーサンプトンシャーではNHSのSLT(言語療法士)がSM治療に積極的に取り組んでいて、本当にラッキーだなと思います。
●ノーサンプトン州における緘黙児支援 SLT(言語療法士)ベス・シェリーさん&ハリエット・ウィルスさん Supporting Children with Selective Mutism in Northamptonshire
<ケアルート>
1) 初回アセスメント
最初のアセスメントには緘黙児を出席させず、まずSLTと保護者だけで面談。
- できるだけ多くの情報を収集
- SMかどうか話し合う
- SMだと思う場合は、これからの治療ルートについてアドバイス
2) 支援チームの基礎作り
緘黙児に関わる人(NHS: SLT、学校心理士?/ 学校:担任、SENCO、TA? / 家庭: 両親?)をできるだけ多く集める
- 場面緘黙とは何か(そうでないケースも説明)
- 緘黙になるリスク要因、引き金要因、持続要因
- 適正な環境づくり:家庭と学校
- キーワーカーの役割
- 子どもに話す勇気を出させる方法
- 支援計画
3) 介入(戦略)
毎日の生活における優先度を考えながら、直接的および間接的な戦略を立てる
- 間接的な援助(子どもが言わんとすることをコメント風に解説/ 質問形式の考慮(まずYes, No形式から)/ 保護者が子どもの代わりに言う場合など)
- CBTのエクスポージャー法(活動やコミュニケーション量は?)
- 優先度に応じた支援計画を立てる
4) 介入(スモールステップのプログラム)
既成のプログラムに加え、子どもの性格を考慮したアプローチにする
- 支援計画の実施
- スライディング・イン法
- その他の介入方法(読本、電話、電子メール、テキストなどを利用)
- 自信のある話し方の模範を見せる
5) 支援プログラムのモニタリングと問題解決
- 資料や活動を関係者でシェア
- 特定の問題を発見・解決
- ケーススタディと実践的なアドバイス
- もし進歩がない場合は、SMが継続する要因を見直す
- 活動プラン練り直し
6) 一般化と次の段階への移行
- 学校で不安に向き合う
- コミュニティ内で不安に向き合う
- 社会的な機能: 自発的な会話への移行
- 移行の支援
- 活動プラン
<ポリシー>
- SMが固定する前に早期発見・介入する
- スモールステップ方式のプログラムを始める前に、子どもをめぐる環境を整え社会的に快適な状態にする
- 緘黙治療に関わるキーパーソンの重要性
- 治療に関わる関係者全員を教育し、子どもの情報を共有する
SLTが中心になって場面緘黙支援を整えた結果、1か月に4人ほどの子ども紹介されてくるようになったとか。
<実例: 9歳の少女ホリーのケース>
緘黙症状: 幼稚園時代に始まり、小学校4年生まで学校では全く話せない。
家庭状況: 両親は離婚しており、母親と同居。母親とは自由に話せるが、父親とは非言語のコミュニケーションのみ。学校では非言語だが、十分なコミュニケーションが取れている状態。
SMを持続させる要因:「しゃべらない子」としてのIDが確立されてしまっていた。母親は「性格的なもの」「成長したら治る」と娘のSMを容認。家族でも、学校でも、「話せるかもしれない」という期待は全くなく、「話す機会」が全く与えられていなかった。
介入の成果: 一回目のミーティングで母親がSMの知識を得、ホリーへの接し方を180度転換。ホリー自身にもSMを説明し、母娘が週に2回学校に行って支援をするように。現在10歳のホリーの緘黙状態は飛躍的に改善し、学校では自発的に話せるよう支援を受けている段階。父親とは普通に会話ができるようになった。
みく備考:このケアルートで大切なポイントは、各セクターで子どもに関わる大人にできるだけ多く支援チームに加わってもらうこと。家庭や学校での子どもの様子、緘黙支援の方法を皆でシェアすることで、サポートにブレがでないと思います。また、保護者にとっても、多くの関係者と直接話す機会があるので、とても心強いでしょう。
また、最初のミーティングは子どもを交えず、SLTと保護者だけというのもいい考えだと思います(この時点で、学校と保護者は連絡が取れているはず)。緘黙児には繊細な子が多いので、話せない場で自分のことを言われるのは嫌でしょうし。保護者が緘黙について知り、自分の子どものことをじっくり話せたら安心できますね。
日本では各クラスにTAがおらず、担任ひとりなので、緘黙支援のキーワーカーをつけるのが難しいですよね…。イギリスではキーワーカーが確保できない場合は、保護者が週に2回ほど学校に行って支援を行うことが多いんですが(小学校低学年)、日本ではそういう訳にはいかないでしょうし…。担任ひとりの努力に任せず、学校で子どもが頼れる人がいるといいなと思います。
<関連記事>
2019年SMiRAコンファレンス
2019年SMiRAコンファレンス(その2)
2019年SMiRAコンファレンス(その3)
2019年SMiRAコンファレンス(その4)
2019年SMiRAコンファレンス(その5)
2019年SMiRAコンファレンス(その6)
2019年SMiRAコンファレンス(その6-2)
2019年SMiRAコンファレンス(その7)
2019年SMiRAコンファレンス(その8)
環境問題の旗手は場面緘黙(その1)
環境問題の旗手は場面緘黙(その2)